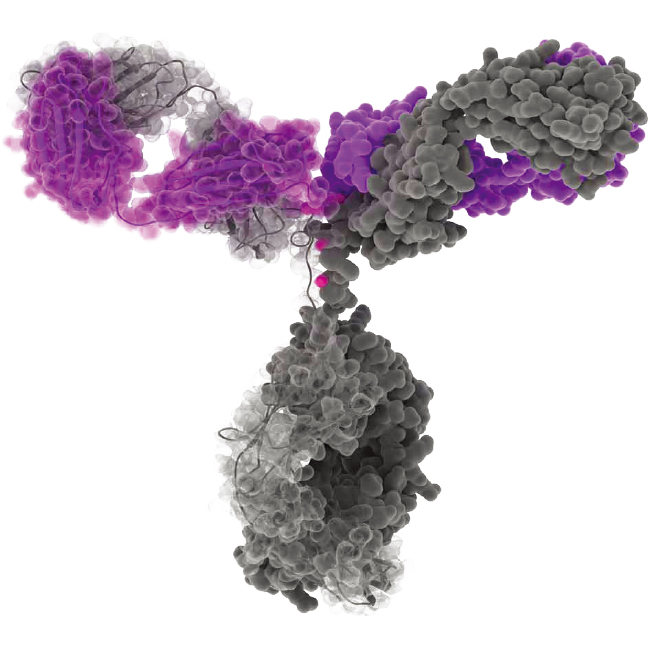ミツバチの性決定の分子スイッチが徐々に環境に適応して進化してきた過程が、200年近く経てようやくアリゾナ州とヨーロッパの研究者によって明らかにされた。性決定の遺伝子的仕組みは1800年代中頃にシレジアの僧侶、Johann Dziersonによって初めて提唱されたが、今回の研究論文の共同著者を務めたArizona State University (ASU) のProvost Robert E. Page Jr. によれば、Dziersonはミツバチのコロニーでオスとメスがつくられる仕組みを理解しようとしたということである。
Dziersonは、女王バチも働きバチもメスであり、餌の質と量の違いによって、機能に違いができてくるということに気づいていた。同時に、オスはどうなるのかという疑問をいだいた。Dziersonは、ミツバチのオスを、染色体を1セットしか持っていない半数体と考えたが、1900年代になって顕微鏡の出現に伴い、その考えが正しいことが確認された。顕微鏡を使って観察した研究者は、雄バチになる卵には精子が侵入しないことに気づいたのである。しかし、この半倍数性性決定システムがどのようにして究極的に分子レベルで進化を遂げることができたのかという疑問は、発生遺伝学の分野で最も重要な疑問のひとつだった。
2013年12月5日付「Current Biology」に掲載された研究論文「Gradual molecular evolution of a sex determination switch in honey bees through incomplete penetrance of femaleness」で、筆頭著者のDr. Pageと、ドイツのUniversity of Duesseldorf, Institute of Evolutionary Geneticsの教授、Dr. Martin Beye、および共同研究者は、このシステムの進化過程で最後まで残っていた謎を解明した。著者らは、ミツバチの76種の遺伝子型を対象に、自然に見られる相補的性決定スイッチ遺伝子変異型 (csd gene) 14種類について研究した。複雑な作業ではあったが、研究チームは性決定性の謎を解くためにいくつかの強力なツールを手にしていた。このようなツールはこの分野の先達が持たなかったものである。まず、ミツバチは、性決定に関わる遺伝子座をたった一つしか持たないため、研究対象とするのに理想的である。
さらに、Dr. Pageと元大学院生のDr. Greg Huntは、相補的性決定遺伝子座に近いDNAの中でもかなり特徴づけが進んでいる領域の遺伝子マーカーを明らかにし、遺伝子マッピングが可能になっている。加えて、Dr. HuntとDr. Pageは、ミツバチの場合、有性生殖の過程で遺伝子物質が物理的に混合される遺伝子組換率が、それまでに研究された動物の中ではもっとも高い事実に気づいた。遺伝子組換率の高さは、Dr. Beyeが相補的性決定遺伝子座を分離、配列解析、特徴づけを行う上で有利に働いた。
Dr. PageとDr. Beyeは、対立遺伝子の働きを止めることで二倍体遺伝子型からでも雄バチをつくることができることを証明した。この研究は2003年の「Cell」誌の表紙に採用されている。
ただし、どの対立遺伝子がカギになるのか、どのように連携しているのか、その組み合わせは、なぜこのシステムが進化したのかなどの疑問は解明の一歩手前で謎のままに残された。そのことは、現在の共同研究チームにも、一歩下がって、何をもって対立遺伝子とするのかを見直すことを否応なくした。ASUでLife SciencesのFoundation Chairも務めるDr. Pageは、「この対立遺伝子群に問題の遺伝子の特定セグメントがあるはずで、その遺伝子のその部分に2つの異なるコーディング配列がある場合は雌バチになる」と述べ、さらに、「そこで、2つの対立遺伝子はどれほど異なっていなければならないのか、1つか2つの塩基対が異なるだけでいいのか、それとも常に同じ配列でなければならないのかと考えた。
結局、研究チームは、18対から20対の対立遺伝子を調べ、いくつもある変異体の中で、遺伝子のどの領域がカギを握っているのかを突き止めようとした。その過程で、中間的な対立遺伝子もあるのかどうかを判断し、それがどのように進化したのかを突き止めなければならなかった」と述べている。
研究チームは、少なくとも5つのアミノ酸の違いが対立遺伝子の違いをもたらし、雌雄を決める制御スイッチ、相補的性決定遺伝子 (csd) を通してハチの雌性を形成することを突き止めた。Dr. Pageは、「アルギニン、セリン、プロリンの量の違いがcsd遺伝子のタンパク結合部位に影響を与え、そのことによって異なる立体配座状態になる。それがさらにハチの機能上の変化をもたらし、雌から非雌に転換するスイッチの役割を果たす」と述べている。また、研究チームは、自然に起きる進化の中間過程で、たった3個のアミノ酸の違いが致死率から誘発的な雌性まで様々な特性の違いをもたらすことを発見した。人類が最初に気づいてからその原因を突き止めるまで200年近くかかったこの現象は、不完全浸透というメカニズムは、新しい分子スイッチが徐々に環境に適応して進化するということなのかもしれない。
Dr. Beye、Dr. Pageの他、共同著者は次の各氏: University of DuesseldorfのDr. Christine SeelmannおよびDr. Tanja Gempe、ドイツのUniversity of Cologne, Institute of GeneticsのDr. Martin Hasslemann、フランスのUniversite LilleのDr. Xavier Bekmans、ASUのDr. Kim Fondrk。Provost Pageは、ASU, Life SciencesのFoundation ChairとSchool of Life Sciencesの教授を務め、著書には「The Spirit of the Hive: The Mechanism of Social Evolution」 (Harvard University Press, 2013) がある。
■原著へのリンクは英語版をご覧ください: Molecular Evolution of Genetic Sex-Determination Switch in Honey Bees